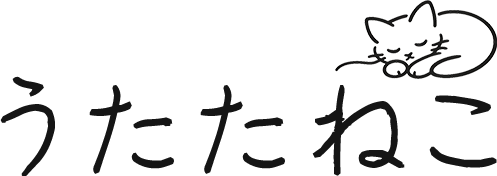カレーではない何か(1)
最初は、たいてい同じだ。
皿に盛られた茶色いソース。
白いごはん。
スプーンを入れる前に、もう頭は「カレー」になっている。
ところが、口に入れた瞬間に違和感が出る。
辛くない。
スパイスの輪郭がない。
でも、まずくはない。
あ、ハヤシか。
そう気づいたところで、食事は何事もなかったように続く。
この一瞬のズレ。
今日はその話をする。
なぜ、私たちは間違えたのか。
理由は単純だ。
色が似ている。
ごはんにかかっている。
家庭の食卓で、同じ位置に置かれてきた。
つまり、味を確かめる前に判断が終わっている。
料理は、舌より先に、目と文脈で食べられている。
これはハヤシに限らない。
だが、ハヤシほどこの条件を完璧に満たした料理はない。
では、それは本当に「間違い」だったのか。
ハヤシライスは、違いを主張しない。
辛さで境界線を引かない。
由来も正体も、積極的に語らない。
これは別の料理です、と言い張る理由がなかった。
家庭に入ったとき、
ハヤシはカレーと同じ鍋で作られ、
同じ皿に盛られ、
同じ日常の一コマとして消費された。
その時点で、勝負は終わっていた。
補足しておくと、
ハヤシライスは日本で生まれ、日本で形づくられた料理だ。
明治期の洋食を起点にしながら、
家庭に入った瞬間、
カレーと同じ生活の棚に並べられた。
市販ルウの時代になると、その関係は完全に固定される。
カレールウの隣に、ハヤシルウ。
別料理だが、別枠ではない。
だから、こう言ったほうが正確だ。
ハヤシライスは、
カレーに間違われた料理であり、
カレーの隣に座ることを選んだ料理でもある。
区別しなくても困らない。
説明しなくても成立する。
その曖昧さこそが、ハヤシの強さだった。
カレーの話をしているつもりで、
私たちは別の料理を食べている。
それでも日常は回り続ける。
ハヤシライスは、
日本人が考えずに食べるために残った料理だった。
次回は、
なぜこの料理には「正体」がないのか。
名前の話をする。