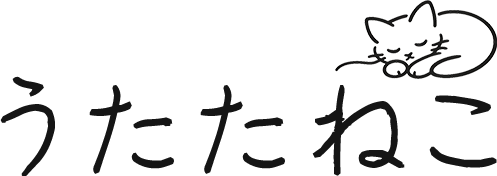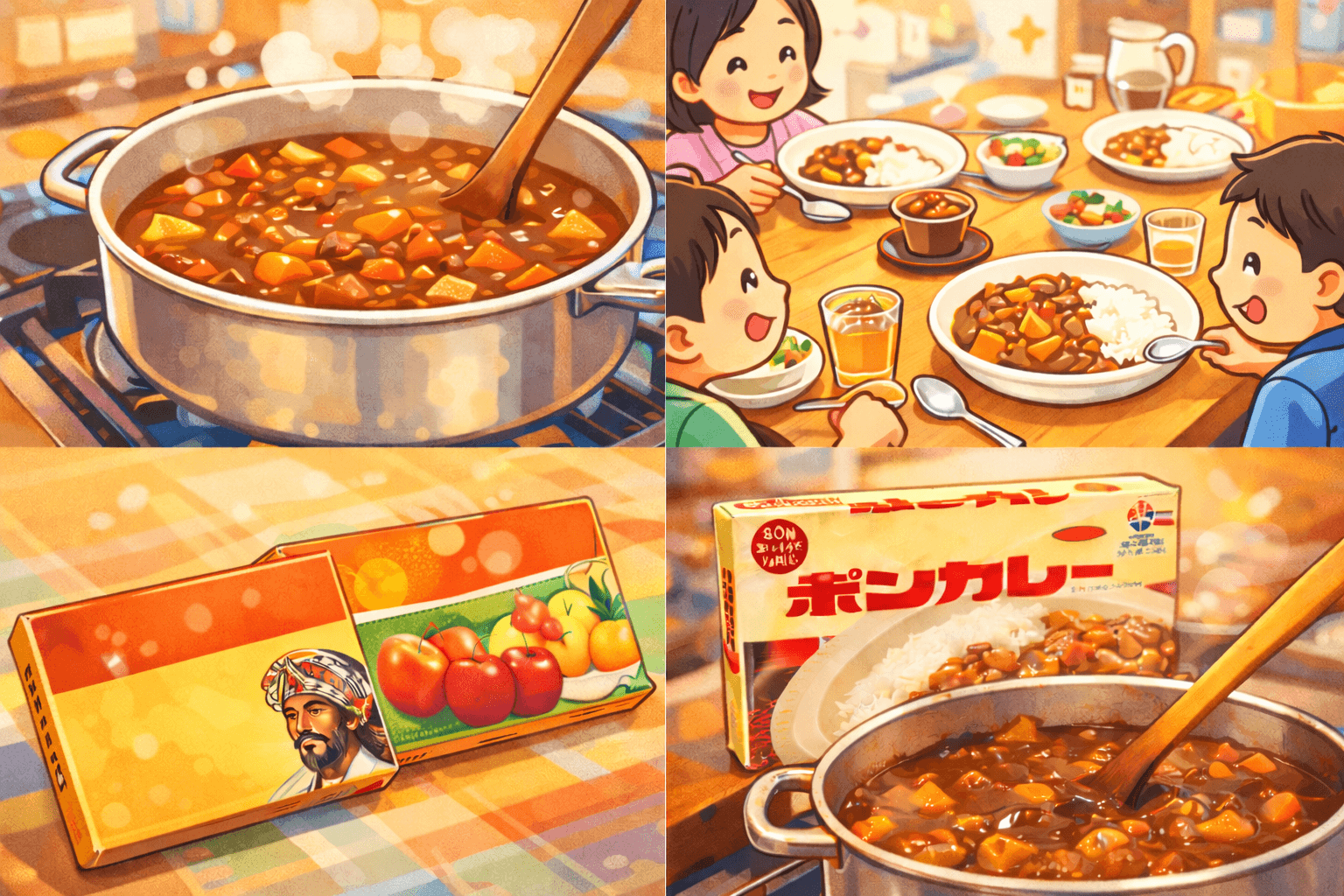家庭料理と外食のあいだ(2)
カレーが家庭料理として完成したのは、
日本人がカレーを愛したからではない。
先に、
家庭の側が受け入れられる構造を
すべて持っていた。
寿司は、家で握らない。
ラーメンを作ろうとしても、家には寸胴がない。
うなぎやフグは、捌こうとすらしない。
それらと比べると、
カレーは異常なほど、
家の台所に馴染んだ。
この違いは、文化ではなく、設計の問題だ。
特別な道具を必要としなかった
カレーに必要なものは、
鍋とコンロだけだった。
圧力釜も、強火も、焼き台もいらない。
家庭の標準装備で成立する。
この条件を満たした料理は、実は少ない。
ラーメンは寸胴が必要だ。
中華は火力と油処理が必要だ。
寿司は道具以前に、技術と素材管理が必要だ。
カレーは、
最初から「家にあるもので作れる料理」だった。
失敗しにくい料理として設計されていた
日本のカレーは、
煮込めば整う。
これは、家庭料理として致命的に重要だ。
多少水が多くても、
具が崩れても、
火を入れすぎても、
致命的な失敗にならない。
この性質を決定づけたのが、
1960年代以降に普及した固形カレールウだ。
1960年、
ハウス食品が「印度カレー」を発売。
1963年には「バーモントカレー」が登場する。
甘口という概念。
子どもでも食べられる設計。
箱の裏に書かれた作り方。
ここで、
カレーは料理ではなく
「再現可能な家庭工程」になった。
匂いと後処理が、家庭に許された
料理は、
食べている時間だけの問題ではない。
作る前と、作った後がある。
カレーは、
匂いが残る。
でもその匂いは、
家庭の匂いとして許された。
豚骨スープの匂いは、
家庭では拒否される。
中華鍋で油を回す音と煙も、
日常には重すぎる。
カレーは、
匂い・油・後片付けの負担が、
家庭の許容量に収まっていた。
食品産業が「家庭料理として完成」させた
ここが、最も重要なポイントだ。
カレーは、
家庭だけで完成した料理ではない。
食品産業が、
家庭料理として完成させた。
1970年代、
レトルトカレーが普及する。
大塚食品の「ボンカレー」は1968年発売。
温めるだけで食べられるカレーが、
家庭の中に入った。
ここで起きたのは、
「作らない家庭料理」の誕生だ。
鍋で作るカレーと、
温めるカレーが、
同じ棚に並ぶ。
この構造は、
ラーメンや寿司には起きなかった。
外で食べる理由が、家庭を上回らなかった
外食カレーは、存在していた。
専門店も、
喫茶店のカレーも、
社員食堂のカレーもあった。
しかし、
家庭カレーを倒しにいかなかった。
なぜなら、
家庭で作る意味が、
最後まで残ったからだ。
安い。
量を調整できる。
翌日に持ち越せる。
失敗しても、家の味になる。
外で食べる必然が、
家庭を超えなかった。
カレーは、家庭料理の条件をすべて満たしていた
設備。
時間。
技術。
匂い。
素材管理。
失敗の許容。
すべてを、
最初から、あるいは産業の力で
クリアしてしまった料理。
それが、カレーだった。
だから、
日本人は今も、
当たり前のようにカレーを作る。
次の話では、
外食カレーは何をしていたのかを見ていく。
家庭に勝てなかったのではない。
最初から、別の役割を引き受けていた。
・ハウス食品株式会社 公式サイト「会社沿革・商品史」
・大塚食品株式会社 公式サイト「ボンカレーの歴史」
・農林水産省 食生活・食品産業に関する公開資料
・日本の食文化史・家庭料理史に関する一般文献
※本記事は、公開情報および一般的な生活実感をもとにした考察です。